
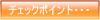
速度に見合った時機から減速しているか?
停止距離は、速度の二乗に比例して長くなるといわれています。
所内教習でそれほど速度が上げられる教習所は少ないでしょう。
初めて路上教習に出たときは、50km/hや60km/hからのブレーキ操作の経験が無いものです。
速度が速くなると、自分が思った以上に停止距離が長くなることを念頭に置いておきましょう。

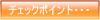
制動開始の直前まで加速していないか?
路上へ出ると、交通の流れに乗るために強い加速が必要なことが多く、常にアクセルを深く踏み込む癖がついてしまうことがあります。
ところが運転はそんな画一的なものではなく、極弱い加速、やや弱い加速、やや強い加速、強い加速と発進してから停止するまでの距離や状況によって加速の度合いを変えなければ流れに合せることができません。
にもかかわらず、常に強い加速をしていると制動開始時期に必要以上に速度が上がってしまい、結果的にブレーキの遅れとなります。
早めにブレーキをかけようと心掛けているのに、急ブレーキぎみになってしまうようであれば無駄な加速を疑ってみてください。
チェック方法は、発進してから停止するまでの間に同じ速度で走行する時間があったかどうかを確かめます。
もし、加速状態からいきなり制動状態に移らなければならないようなら、無駄な加速をしているといえるでしょう。
発進してから停止するまでの間には、できるだけ同じ速度で走行する時間を作りましょう。

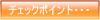
ブレーキを踏む力が弱くないか?
所内のように低速で走行しているときと同じ力でブレーキペダルを踏んでいたのではどうしてもブレーキの効きが悪くなります。
ブレーキには速度が速ければ早いほど効きが悪くなり、速度が遅ければ遅いほど効きがよくなる性質があるからです。
つまり、速度が速いときはブレーキペダルをある程度強く踏み、速度が落ちてくるにしたがって徐々に弱くしていく必要があるのです。
制動前半のブレーキが弱いとどうしても後で強くブレーキを踏まなければならず、結果的に制動が遅れ急ブレーキになります。

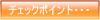
間違えた断続ブレーキを使っていないか?
『運転教本』には断続ブレーキの重要性について書いてありますが、その具体的な方法についてあまり書いていないので、間違えた方法で覚えている人もいるようです。
代表的な例は、ブレーキペダルを踏み込んでいってパッと戻し、また踏み込んでいってパッと戻すを繰り返す断続ブレーキです。
この方法ですと、どのくらい速度が落ちたかを感知する前にブレーキペダルを戻すことになり、制動が遅れることが多くなります。
停止するときのショックも大きくなり、乗り心地の悪い運転にもなってしまいます。
正しい断続ブレーキの使い方は、ブレーキペダルを軽く踏んで戻し(制動灯点灯)、次に必要な強さまで踏み込んでいったら同じ強さを維持し、じゅうぶんに速度が落ちてきたことを確かめてからそっとペダルを戻します。(一次制動)
同じ強さで踏むといっても、踏んでいる間にブレーキの効きを感知し微妙に力加減をコントロールしてください。
そして、二次制動も同じ要領で行いますが、一次制動より速度が落ちているはずですからやや弱い力でブレーキペダルを踏むことになります。
余裕を持った断続ブレーキが使えるようにしてください。
備考Ⅰ
ブレーキペダルを戻す余裕が無いときは、断続ブレーキを使ってはいけません。
また、速度が概ね20km/h以下のときは、断続ブレーキを使う必要はありません。
備考Ⅱ
断続ブレーキは、細かく何回も踏み分ける必要はありません。逆効果になることがあります。
二次制動から三次制動ぐらいまでできれば十分です。

関連項目





